戸籍簡易用語集
家系図を作る上で戸籍に出てくる言葉を紹介します。
もしその他分からない単語等あれば、みそらまでご連絡下さい。
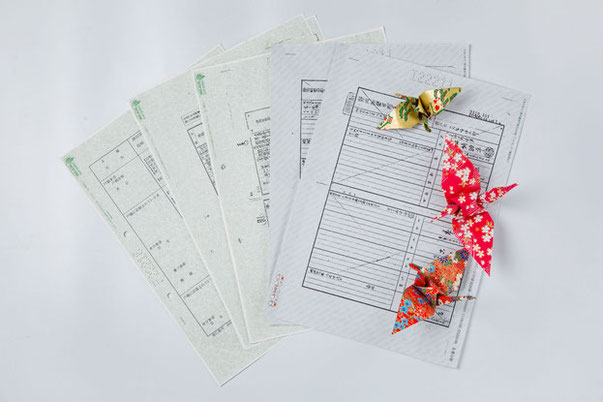
1.戸籍(証明書)
出生から死亡までの身分行為(出生・結婚・出産・離婚・死亡・子の出生・認知・養子縁組・離縁・家督相続・隠居)など
2.除籍(証明書)
死亡・離婚・転籍・婚姻・子の生・分籍・離縁・分家などで籍が抜けたこと。
転籍などにより、一つの戸籍の中にいる者全員が除かれた戸籍を指します。また、婚姻などにより、個人がその戸籍から除かれることも表します。 ちなみに通常「除籍謄本」という言葉は全員が除籍になった戸籍で、全員分が載ったものを表します。 除籍謄本の保存期限は全員が除籍になった日から150年です。以前は80年でした。
3.改製原戸籍 (原戸籍)
改製前の戸籍を改製原戸籍という。
昭和改製原戸籍 家・戸主制度 縦書き
平成改製原戸籍 S22~S33年 いわゆる移行期間のようなもの 夫婦単位(2世代まで 夫婦+未婚の子) 縦書き
コンピューター化 平成11年7月24日~(浜松市の場合)(平成の改製H6) 横書き
※引き継がれる前の状況は載らない。
本籍・筆頭者はインデックス(目次)のようなものと捉えるとよいかもしれません。
除籍は届出により、除かれた記載をした戸籍をいいます。 改製原戸籍とは同じく除かれた記載をした戸籍なのですが、届出ではなく、戸籍の記載方法の改正などにより新しくつくり直した元の戸籍を指します。 戸籍法が明治4年に公布されて以来、何度か大きな改正により戸籍が書き直されています。
*明治5年、明治19年、明治31年、昭和22年、平成6年に改正が行われている。
4.戸籍の附票
住所の履歴。戸籍上の人物の住所について記録した資料
5.謄本・全部事項証明書
戸籍に載っている方全員の証明書。原本が紙の戸籍での証明を謄本、電算化になっている戸籍の証明を全部事項証明という。
6.抄本・個人(一部)事項証明
戸籍抄本、戸籍個人事項証明
戸籍に載っている方個人の証明書。原本が紙の戸籍での証明を抄本、電算化になっている戸籍の証明を個人事項証明という。
7.現在戸籍
現在生きている戸籍。婚姻、養子縁組、分籍などにより現在の戸籍から抜けると、もとの戸籍には除籍の記載(記録)がされ、そして、 新しくつくった戸籍や新しく入った戸籍に現在戸籍として記載(記録)されます。
8.戸籍筆頭者
各戸籍の最初に記載される人。
9.本籍
人の戸籍の所在する場所。
10.入籍
ある者が戸籍に記載されること。戸籍にはいること。又、入れること。
11.分家
家族の一員がその属する家から離れて新しく所帯をかまえること。
12.転籍
本籍地を変更する。理由は問わない。出生・認知・養子縁組時に多い。
地番があればどこでもOK。浜松市役所、皇居などもあり。 結婚しなくても自分の戸籍を作る。
20歳で可。本人が筆頭者。
13.復籍
前の戸籍に入る。離婚して、親の戸籍に戻ることなど。一つ前までのみ。
離婚しても婚姻時の氏を名乗ることも可能(離婚後3か月以内に申請)
小中学校の子を持つシングルマザーに多い。
14.養子縁組
婚姻・離婚・子の出生・養子縁組などの場合が多い。
血のつながりにおいて親子ではない者の間に法律上、実の親子と同じ関係を成立させる契約。
養子縁組による戸籍の記載状況・養親との苗字の記載状況については多様。
・養子が単身者や既婚者の場合
・養親の現在戸籍に入籍する。
・養親が新戸籍編成する。
・養子夫婦で新戸籍編成する。
・身分事項への記載のみ。 など、多様で難しい。
留意事項は「現在」の氏(苗字)が何であるかを把握すること。
●特別養子縁組(民法817条の2)
令和元年6.8まで
養子の条件:は6歳未満。
養親の条件:25歳以上、夫婦であること
実親との親子関係なしとなる。養親の実子となる。
(戸籍上判明不能と言われるが、前戸籍に<817-2>の記載がある)
●特別養子縁組
令和元年6.9から
養子の条件:は15歳未満。(原則)
養親の条件:25歳以上、夫婦であること
実親の同意必要 6ヶ月以上の試験養育必要
実親との親子関係なしとなる。養親の実子となる。
15.禁治産者
1999年(平成11)の民法改正(2000年4月1日施行)で導入された成年後見制度の前に設けられていた禁治産・準禁治産宣告制度の下で、「禁治産者」は「心神喪失の常況」(精神に障害があって、ときに正常に復することはあっても、おおむね正常な判断能力を欠く状態)にあるため、家庭裁判所から禁治産の宣告を受け、まだその宣告が取り消されていない者をさしていた。
16.後見人
判断能力が不十分と考えられる者を補佐する者。法律上の後見人は、財産に関するすべての事項で、未成年者あるいは成年被後見人の法定代理人となる者をいう。ただし、未成年者の場合には、本来、法定代理人となるべき親権を行う者(親権者: 父母、養親)がいないとき、または、親権者に財産管理権がないときにのみ後見人は置かれることになる(民法838条1号)。
17.家督相続
民法旧規定。戸籍上の戸主の死亡・隠居により一人の相続人が身分・財産を相続する。直系卑属の中から一人の相続人(主に長男)が選ばれた。戦後、家制度とともに廃止となる。旧民法 (明治31年7月16日~昭和22年5月2日) ここで言う「戸主」とは、単なる戸籍の筆頭者ではなく、家名・家業・家族の財産の3つが一体となった「家督」を所有する人を指します。
18.隠居(隠退)
戸主が生前に一家の代表者を降り、新しい戸主へ家の権限を渡すこと。
昭和22年戸主制度廃止と共になくなる。
※ 退隠とは「職を退き、暇な身分となること」で戸籍上は、隠居と同様に扱われている。
19.新戸籍編成
婚姻等により、新たに戸籍を作成すること。
20.戸主
昭和22年(S23以降の戸籍に表記はない)まで旧民法で、家の統率者。戸籍の代表者。戸主権を有し、家族を統括し扶養する義務を負う。戸主を中心とした一族全員は載っている。
21.前戸主
現在の戸主の前の戸主のこと
22.廃嫡
旧民法で、被相続人の意志に基づいて推定相続人の家督相続権をなくすこと。
23.妻携帯
分家に際し父母を伴って新戸籍に入籍。
24.直系尊属
自分を中心として父祖の世代(縦の流れ)配偶者の父母も属する。
25.直系卑属
自分を中心として子孫の世代(縦の流れ)
26.親族
血族と姻族
27.血族
血のつながりのある親族
28.姻族
一方の配偶者と他方の配偶者の血族との関係
29.傍系
祖を同じにする横のつながり。叔父叔母・兄弟姉妹など。
30.過去帳
日本の仏具の1つで、故人の戒名(法号・法名)・俗名・死亡年月日・享年(行年)などを記しておく帳簿である。鬼籍あるいは点鬼簿と呼ぶことがある
31.戒名
仏教において、戒を守ることを誓った(受戒した)者に与えられる名前である。
仏門に入った証であり、戒律を守る証として与えられる。
32.絶家
戸主の死亡などでその家に家督相続人がいない場合を「絶家」という。子どもがおらず、跡継ぎや相続人などもいないという理由から、お墓や家系を承継できる人がいなくなってしまう事をいいます。江戸時代には『絶家帳』というものがありました。
33.廃家
戸主の婚約や養子縁組などの戸主の意思による理由で家を消滅させること
34.廃絶再興
廃絶家を縁故者が戸主となり再興する。氏を名のる。前の家の財産や権利を引き継ぐわけではない。家の名を残すもの。
→時々戸籍に見ることが出来ます。初めてこの言葉に出会った時には、思わず感動した制度です。
それだけ家を守ることが大切な時代だったということですね。(塩崎)
株式会社みそら /監修:行政書士法人みそら
〒435-0042 静岡県浜松市中央区篠ヶ瀬町1324
TEL:053-545-9172
FAX:053-545-9176
HP : https://www.misora.biz
mail : misora.kakeizu@gmail.com
minne :「@misora-0901」で検索!
